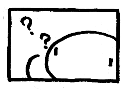■京都市バス
○山越
個人的に一番好きな終点。なぜと言われても困るが。
○大覚寺
○上賀茂神社
ロータリーを越えた上賀茂神社の前。
○久我石原町
○岩倉操車場
○横大路車庫
■京都バス
○広河原
左京区の果て。ここから先は冬期通行止めとなる。
○清滝
○岩倉実相院
岩倉実相院の正面が終点。実相院の門の右手がバスの待機場所。
○苔寺・すず虫寺
○岩倉村松
■京阪京都交通
○長峰
道路脇のぽっかりと空いた場所にこじんまりと納まる終点。なかなかいい感じの終点。
■京都バス
○大宅
営業所であり、あまり終点ぽくない。
■阪急バス
○善峯寺
検索結果
+ 2006年12月06日(Wed)
+ 岩倉実相院
技術士二次試験の口頭試問とか何とかで余裕が無く、紅葉の時期をすっかり逃してしまった。残念だが、未練がましく岩倉実相院に行ってみる。
実相院は天台宗の門跡寺院である。黒光りする床に窓の向こうの紅葉が反射する床紅葉が有名だ。なお床紅葉は写真撮影禁止。どうでもいいが注意書きが多い。
すっかり紅葉は終わっていた。庭には散ったモミジの葉が残されていた。
なお、岩倉実相院は京都バスの終点でもあったりする。これはこれでバスの終点好きにはたまらない。
帰りに、岩倉具視幽邸を見学して、叡電の岩倉駅まで歩く。
+ 2007年02月22日(Thu)
+ 唐櫃越
天気も良いので唐櫃越(からとごえ)に行って来た。唐櫃越は、亀岡と京都の間道。古くは太平記などにも登場する。近年では明智光秀が本能寺攻めのための移動に使ったのではないかといわれている。
歴史的には京都へ隠密裡に攻め入るために用いられたことから亀岡から京都に行くのが正しいのかもしれないが、時間の都合で京都から、しかも常道である上桂からではなく、京都バスの終点である苔寺・すず虫寺からスタートする。
○京都バス「苔寺・すず虫寺」バス停(12:00)〜桂坂野鳥観察園(13:00)
バスを降り、東海自然歩道に沿って竹の寺の前を通り過ぎてすぐの十字路を右の山の方向へ。ちなみに左に行くと「山田岐れ」を経て上桂の駅へ、真っ直ぐ行くと東海自然歩道に沿って進むことになる。
住宅地がとぎれ、竹林の中を少し進むと、墓地に行き当たる。墓地の一番上の部分では京都の街が見渡せる。これは、やはり逆向きに来るのがよいのだろうなあ。
そこからは山中の道となる。といっても北山のように鬱蒼たる杉林ということではなく、竹林や落葉樹主体で、気持ちのよい道である。GPSも感度良好。
テープで脇にそれる道があったので少しそちらへ進んでみると、桂坂の住宅地の裏側に出て、桂から大原野が一望に見渡せる。霞んでいるのが非常に残念である。
さらに進んで、スタートから1時間ぐらいで、桂坂の野鳥園にでる。整備されており、ベンチなどがあったり、大原野方面への眺望がひらける場所がある。食事をとるなら、この周辺がよいと思われる。
○桂坂野鳥観察園(13:00)〜沓掛山三角点(13:25)〜林道出合(14:10)
しばらく進むと、沓掛山の三角点近傍を通る。少し脇にそれるが三角点に立ち寄っておく。三角点周辺は狭いが開かれている。ここで食事をとる。
そこからさらに進むと、京都・亀岡市境、古くは山城・丹波国境の天蓋峠にでる。天蓋峠に境界を示すっぽいものを探したが、これというものはみつからず。峠の脇のピークに境界石があったが、単なる敷地境界にすぎないかも。
そこから少し下ると、舗装道路に出る。ここでちょうど出発から2時間。この舗装道路を左に進むと西山団地を経て、老ノ坂のバス停に出るようだ。この舗装道路を右に進む。舗装道路を淡々と歩く。
○林道出合(14:10)〜みすぎ山三角点(15:05)
ただ舗装道路を歩くのだが、しばらくすると北東方向への眺望が右手にひらけ、愛宕山が見えるようになる。今度はあれに登ろうと思いながら道を進む。
コンクリート舗装の林道が下からつながり、アスファルト舗装が切れた所で広場があらわれる。ここから砂利舗装の道を進む。
しばらく進んだところ、最初の送電鉄塔が真正面になる地点に、林道から外れて正式なルートはこちらということが書かれた私設の案内があるが、迷いやすいともあり、林道を進むことにする。
北側を巻いていくルートを進むと、大きな送電線の下をくぐる。送電線は保津川を越えて水尾のほうから伸びている。保津川に電車が通りかかったようで電車の轟音がこだまして届いてくる。
1本目の送電線を越え、2本目の送電線にさしかかるところで林道が終わり、再び歩道に変わる。少し歩くと視界が開け、みすぎ山のピークに出る。
○みすぎ山三角点(15:05)〜宝泉寺(15:40)〜馬堀駅(16:00)
みすぎ山のピーク周辺は、近傍に送電鉄塔がありその管理のためか、木が切りひらかれており、亀岡(馬堀)への見下ろしの眺望がよい。山頂には二等三角点がある。
そこから降りる道へ進路を取る。これまでの緩やかな傾斜の道とは違って、かなりの急傾斜を進む。石垣が組まれた場所を通り、イノシシよけの扉を過ぎると、程なく宝泉寺にでる。
そこから鵜の川を渡って、住宅地を通り過ぎて、馬堀駅に着く。
ちょうど16時。ということはちょうど4時間の行程であった。
○感想と総括
霞んで眺望があまり利かなかった。残念。
歴史的な雰囲気を感じるなら、亀岡側から来るのがよいかな、と思った。京都側から入ると、きつい登りがないのでらくちんではある。
現在のハイキングコースとしての唐櫃越に沿って進んだが、昔は王子村に降りたとか、篠村でももう少し王子側に降りたとかという情報もある。
足利先生は、光秀は愛宕山方面に進み、途中で進路を変え、保津川を渡渉して唐櫃越に合流したのではという推測をしている。現在、そのルートを取ることはできないが、なかなか興味のそそられる推測である。
+ 2008年02月19日(Tue)
+ 樫原廃寺
担当していたイベントも終わり一段落したので、午後半休を取って、新しいデジタルカメラを持って、散歩に行くことにした。京都バスの終点(苔寺・すず虫寺)からスタート。地蔵院の脇を通り南下する。道なりに進んで京都桂病院の前を通り国道9号に出た向かいの天皇の杜古墳を見る。さらに南下し、途中樫原の街並みへと寄り道をしながら、三ノ宮神社へ。三ノ宮神社の南側にある樫原廃寺を見たところで、帰途に着く。樫原の交差点から旧山陰街道沿いに歩き、桂駅へ。桂駅で栄養補給した後、新設された70号系統に乗り太秦天神川駅へ。太秦天神川駅周辺は、地下鉄の駅以外はまだすべて工事中でした。
+ 2009年12月27日(Sun)
+ 岩倉と横大路
観光一日乗車券で、京都市のはじっこをバスで巡る。
○岩倉村松
北大路駅から京都バス46系統で岩倉村松へ。岩倉村松停留所は住宅地の奥にありました。テラスハウスというのでしょうか、連棟建ての住宅が多くありました。
帰りは京都バス29系統で国際会館駅へ。住宅地の細かい道を走るなかなか楽しい路線でした。
○岩倉操車場前
市バスの終点。京都バスの停留所名は「宝ヶ池通」。ここから5系統に乗って70分掛けて京都駅へ。銀閣寺・永観堂・平安神宮・河原町三条・四条河原町・四条烏丸とメジャーなところを進み、道も車内も混むので、あまり楽しくない路線です。
○横大路車庫
竹田駅東口から南8系統で横大路車庫前へ。こちらも市バスの終点。一部均一区間外を走るが、最終的に運賃は220円。
○20系統
横大路車庫から、羽束師で桂川を渡り、免許試験所前から桂川の右岸を走り、宮前橋を渡り、旧京阪国道を進み、また横大路車庫に戻ります。いくつかの便は淀まで行くようです。
横大路車庫から、特81系統で竹田駅東口まで。どこかで乗車していたと思っていたが、まだ乗ったことは無かったようでした。
+ 2010年05月02日(Sun)
+ ポンポン山登頂
GW二日目。非常に良い天気。
どこかへ出かけようと考え、最近運動してないなと感じたので、ポンポン山に行くことにした。ポンポン山は京都西山の一座。標高678.9メートル。
インターネットと山の地図(昭文社の「山と高原地図」。この山の地図は標準時刻も書いてあって、ルートを考えるときには超便利!)をにらみながら、アクセスとルートをいろいろと考えた結果、向日町駅からバスで善峯寺まで行き、そこからポンポン山山頂に登り、帰りは高槻市(旧樫田村)方面に降り、高槻市営バスで帰るというルートを取ることにした。さて出発。
○阪急バス66系統善峯寺行(JR向日町駅12:17発)
先日、桜をみるために花の寺こと勝持寺に行ったわけであるが、またの西山行きである。
西山方面に公共交通機関で取り付こうとすれば、京阪京都交通で長峰か、市バス・阪急バス・京阪京都交通で南春日町か、この阪急バスの灰方、小塩、善峯寺である。やはり、お手軽登山であることを考えると、便数もそこそこあって高標高地まで行ける善峯寺に分がある。
JR向日町駅を出たバスは、阪急東向日駅にある営業所の中にいったん入ったあと転回して、停留所に入る。途中で向日市から京都市西京区に入り灰方へ。灰方からはナビゲータが前方出口ステップに立ち、安全を確認しながら進む。ちょうど筍のシーズン。小塩のバス停では筍が500円で売っていた。2~3本入ったかごでその料金のようだったが、1本であっても結構安い。
ぐっと勾配を上げ、善峯寺に着く。すでに多くの観光客が折り返しを待っていた。
○善峯寺(12:50)→杉谷(13:15)→鉄塔(13:35)→ポンポン山山頂(13:55)
バス停から杉谷に向かう。杉谷までは4年ほど前の無職時代にたどったことのあるルートである。バス停からは結構な勾配であるが舗装された道が続く。出だしということを考えると結構ハードな登りである。そういえば、前回来たときは平日で、小学生を乗せた軽自動車が上がっていったことを思い出したが、今回は車にも出会うことなく杉谷へ。
杉谷には飲料の自動販売機がある。ここで追加の飲み物を調達して、ポンポン山方面へ。前回は金蔵寺方面へ向かうために、ここから分岐した。
杉谷からは谷間の田んぼ脇、杉林、雑木林と標高を上げていき、15分ぐらいの所で京都方面への眺望が得られるところに出る。ここから勾配のなだらかに尾根道になり、鉄塔に出る。
ここからは、釈迦岳、島本町方面に降りる道が分岐している。鉄塔下で水分補給を行い、山頂へ向かう。
20分ほどで着いたポンポン山山頂は結構な人出。山頂付近の木を伐採していることから、京都方面への眺望はよく開けている。
さて「ポンポン山」の名前の由来となるように、本当に歩くとポンポンなるかどうかであるが、尾根道で乾燥していればポフポフと音はなる。名付けはそのためなのだろうか。ポンポン山と呼ばれるようになったのは近年とのことであるがよくわからない。
○ポンポン山山頂(14:15)→鬼条語橋(14:50)
山頂で写真を撮ったり、食料を食べたりした後、出発。
ここからのルートとしては、大原野森林公園・大原野外畑町を経て、府県境を越えたところにある中畑回転場に行くか、それとも出灰に降りるかのルートがある。バスの時間を考え、今回は出灰に降り、その時の調子で、出灰からバスに乗るか、北上して中畑まで行くか考えることにした。
山頂からのルートは結構な勾配の階段道が続く。こちらから登るのは結構大変だろうなと思いながら降りていく。途中、道標のあるところで、小さく「→西尾根」という小さな道標が設けられた分岐があった。あとあと考えるとここが大原野自然公園へのルートであったようだ。
途中、眺望が得られたのは1箇所。そこから、愛宕山が望めた。それ以外は急な山道である。降り進んでいると膝を痛めてしまった。今度からストックだろうか。杉林に到達し、あともう少しで人里だと思いながら我慢して進み、鬼条語橋に至る。
○鬼条語橋にて
鬼条語橋は京都・大阪府境である。橋のこちら側は京都府京都市であり、渡れば大阪府高槻市である。橋のたもとには、京都市のごみ集積場を示す見慣れた看板があり、確かに橋の向こう側は京都市であることがわかる。
膝の痛みは、下り段差でなければ問題ないようであり、鬼条語橋で地図を見ながらどちらに進もうか考えていると、山の方から若い男女が降りてきた。そうこうしていると「善峯寺に行きたいのですが、どう行ったらよいでしょうか?」と話しかけられた。
善峯寺といえば私がスタートした地点。このカップルはポンポン山山頂で見たような覚えがあるので、なぜ、反対方向に降りたのだろうかと考えながら、「善峯寺は反対側ですよ」と答える。
話を聞いているとどうやら大原野自然公園に行きたかったようだが、分岐がわからずついに降りてしまったようだ。なんとなんと。山に登り返さず行くルートも聞かれたが、山にのぼるよりも多くの時間が掛かること、バスに乗っていっても、善峯寺までのバスがもうないであろうことを説明すると、あきらめて山に登り返すようだったので、地図を携帯電話のカメラで撮るよう促した。
○鬼条語橋(15:00)→中畑<府道733号線出合>(15:30)→中畑回転場(15:40)
時間をにらみながら、中畑まで上がってもバスの時間には余裕があるようだったので、そちらの方面へ進む。川沿いの道は単調であるが、心地よい陽気の中淡々と歩くことが出来る。途中、橋を渡る部分があり、地図上は京都市であるように見える部分があったが、カーブミラーには高槻市という表示があるなど京都市であるということは判別できなかった。
やがて田植え中の中畑の集落に着き、府道に出る。2車線の府道を登っていくと、程なく中畑回転場バス停に着く。
バスの発車まで30分ぐらいの余裕があったので、府境を越えて大原野外畑町(とのはたちょう)まで行ってみることにした。中畑回転場から歩いてものの5分の所に府境はあり、そのすぐ向こうにきのこ栽培所、花卉栽培所が位置し、その向こうに巨大な変電所が高台の上に位置しているのが見える。
この大原野外畑町、高槻市側から来る道はしっかりしているが、京都市側からは非常に細い道を延々行く必要がある。延々行くと金蔵寺を経て、京阪京都交通の長峰バス停に出る。
○中畑回転場(11JR高槻駅北行き16:17発)
中畑回転場は高槻市営バスのバスの終点である。高槻市の最北部、旧樫田村に位置する。この樫田村、昭和の大合併前には京都府に位置していた。また、旧国で言えば丹波国である。
ということは、先ほどの峠は昭和の大合併前は単なる村境であった訳だ。しかし、城丹国境であることには変わりがないのか。しかし、中畑、外畑とみると名前のつながりはあるように思われる。
転回場はチェーンが掛けてあり、バスは入らないのだろうかと思っていたら、16時頃到着したバスの運転手が降りて鍵を開けてチェーンを外してバスを乗り入れた。バスには私のほかに6人ほどの団体を乗せ、定刻に出発。運転手はいったんバス停を出た上で、転回場のチェーンの鍵を掛け、JR高槻駅に向けて出発した。
ちなみに、11という番号は系統ではなく行き先を示すものらしい。